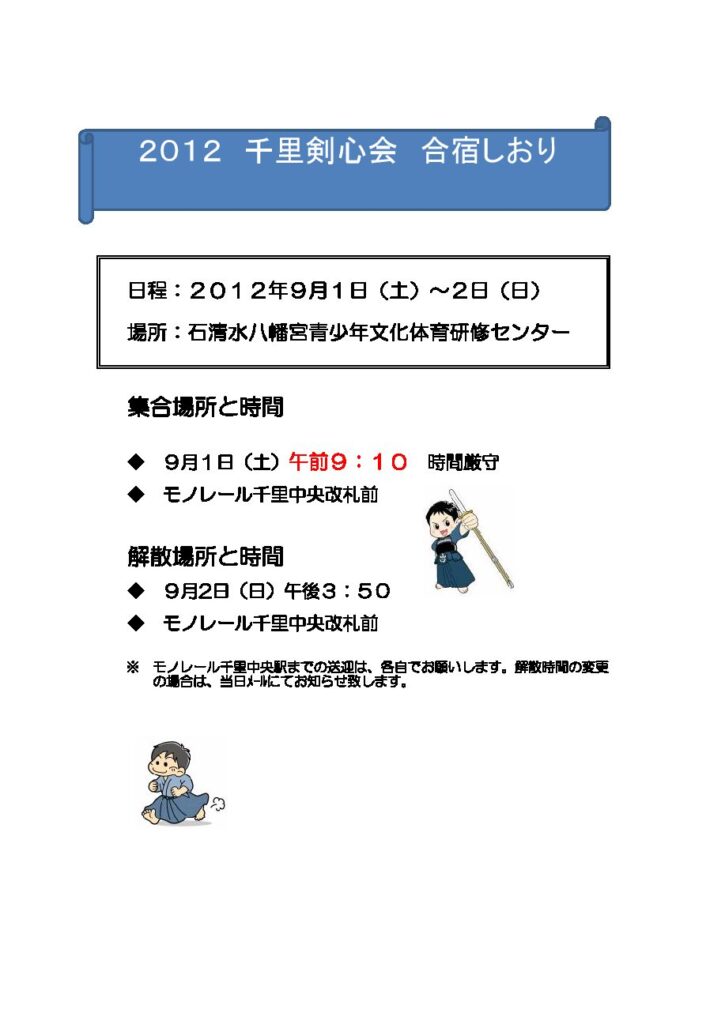実践の攻め_桜木哲史先生
10月 11
桜木哲史先生は、福岡県柳川市出身、1949年(昭和24年)1月17日生まれの剣士で、第16,18回全日本学生優勝大会優勝、第2回世界選手権大会個人戦優勝ほか数々の大会で好成績をあげ、強烈な攻めから放たれるまっすぐな面が持ち味の先生です。
ベースボールマガジン社のムック本「剣道・攻めの極意」から取材記事の一部を抜粋しました。
- 先に打つ、仕掛ける、とにかく前に出る勇気を持つこと。
- 崩れたうちは技前の準備不測を露呈した残骸といっても過言ではない
- 心・気・力を充実させて、上から乗っていく。究極の攻めは一つ。
- 戦いの手順ーーー「目で見て、頭で考え、足で打つ」
桜木先生は、「捨て身の技」という表現に対して、不安要素を持ちながらうっていく悲壮感を漂わせたものと解釈しているそうです。しかし、本来は、悲しい結果とならないために99%の確率を持って1本に出来るように精進していくのが本当の意味での攻めの極意であろうと語っています。
- 真の1本は、攻めが極まったところに放つからこそ、まさに値千金の価値。
- 単純明快こそ、攻めの極意
上から乗って、相手の枕をほんの一瞬だけ抑えて真っ直ぐに打っていくだけ。桜木先生は、相対する攻め合いの中で、一体どうすれば有効打突が打てるのかということを瞬間瞬間に放つ一本に答えを求め、その答えを導き出していくのが剣道だと語ります。
そして、無駄打ちには二つあるといい、「意味のない単なる無駄打ち」をやめ、「結果的に無駄」を繰り返すことで昇華されていくであろうという意味での無駄打ちを繰り返すなかで、しだい次第に”絶対”を求めていくようになると述べています。
以上、
究極を言えば、剣道は「竹刀を真っ直ぐ上げて真っ直ぐおろす」だけの運動ですので、非常に単純といえば単純です。
しかし、相対した相手に対して真っ直ぐ上げておろすだけの面打ちが、如何に難しいことでしょうか!!
「ただ、真っ直ぐに上げておろすだけ」の前にしっかり攻めがあるからこそ、すばらしい一本になるのでしょう。
 RSS
RSS